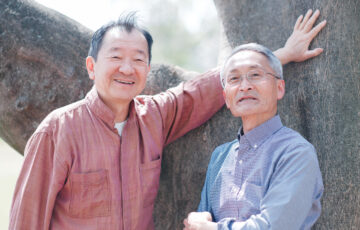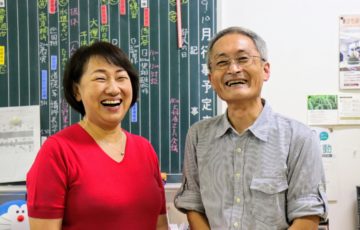古賀野々華(ジャーナリスト・研究員志望)×伊沢正名(糞土師)

日本で原爆、と聞けば、広島や長崎の凄惨な被害や、核兵器の恐ろしさが連想されます。しかし古賀野々華さんがアメリカ留学時代に感じたのは、原爆をめぐる日米の意識の差でした。現在、核の安全性をめぐる研究員を志すようになったという古賀さんに、お話を聞きました。
伊沢:古賀さんを知ったのは、ある新聞記事がきっかけでした。そこでは留学したアメリカの学校で原爆を誇りにしていることに驚き、きのこ雲の下で起きた事について英語でスピーチを行ったことが紹介されていました。
古賀:そうなんです。高校時代にアメリカに留学したんですが、その地域は原爆の製造に関わっていた歴史があり、学校のロゴマークが原爆のキノコ雲だったんです。その驚きが、その後の活動の始まりでした。原爆投下の歴史について、アメリカには原爆に誇りを持っている人もいれば、罪悪感を持っている人もいます。例えば、広島に興味を持って訪れたけれど、自分のことをカナダ人だと偽った知人もいました。こういうふうに、原爆を投下したアメリカ人の一人であることに罪悪感を持っている人もいるんです。


伊沢:それは知りませんでした。原爆に誇りを持っている人というのは、原爆のお陰で戦争が終わったと思っているわけですね?
古賀:そうです。それに加えて、以前は人口数百人の田舎の街だったのが、原爆製造の工場ができたことで人口が増加し、ショッピングモールやレストランもできて街が発展した。そこに誇りを持っている、というケースもあります。
伊沢:なるほど。原爆によって戦争が終わったということだけでなく、街の発展に原爆が役立った、ということですね。日本では原子力発電所のある地域でも同じことが言えますよね。原発ができたことで補助金が入り、豊かな生活ができるようになった地域は多いです。例えば茨城県東海村のように、経済的に潤い、雇用も生まれたんです。
しかしその裏で、放射能被害が隠されている現実もあります。アメリカではどうでしたか?
古賀:アメリカでは、原爆による放射能被害が隠されている場合もあれば、住民自身が気づいていないこともありました。または気づいていても被害を訴えにくい状況もあります。
伊沢:それは日本でも同じですね。被害を公にすると風評被害を招くと周りから圧力がかかることもある。世界中どこでもその構図は同じですね。ところで、アメリカで原爆の実態を知らない人は、どのくらいいるのですか?
古賀:70パーセントくらいでしょうか。
伊沢:そんなに多いんですか!だから古賀さんは、原爆の実態を多くのアメリカ人に知ってもらおうとしたわけですね。私もほとんどが知られていない野糞やウンコの素晴らしさを、多くの人に知ってもらいたいと活動しているんです。例えば、生きるためには食べることが一番大事だとみんな考えますよね。でも、食べれば出るウンコを我慢し切れますか?生きるためには出すことも同じくらい大事なはずです。食べて栄養を得ることと、排泄することの重要性は、パーセンテージでいえばどのくらいになると思います?
古賀:50、50ですか?
伊沢:と思うでしょう。私はそれを、7対3だと考えているんです。例えばヨガの呼吸法では、吐くことしか言わないですよね。吸うことより、むしろ吐くことが重要なんです。人間は水だけでも一週間は生きられますが、一週間空腹を我慢するのと、一週間出さずにいるのと、どちらが苦しいでしょう。そう考えれば、出すことは実はものすごく大事なことなんです。

古賀:大学三年時に、再度アメリカの同じ場所を訪問しました。原爆を製造したアメリカ人が何を考えているのかを知りたいと思い、フィールドワークをしたところ、原爆を製造した側にも被曝者がいることを知りました。衝撃的でした。それまで私は、アメリカが加害者で日本が被害者だと単純な構図でしか捉えていなかったんですが、実は日米両国に被害者がいるんです。そして被害を受けた人々に共通しているのは、何も戦争に関与していなかった普通の市民たちであったということで、一方で加害者になったのは、力を持っている大企業や政府だった、ということです。広島や長崎の人々も、日本の犠牲の一部になっただけで、もしかしたら原爆は東京に落とされていたかもしれなかった。それを広島や長崎が犠牲を払ったという構図があることに気づいたんです。
伊沢:もし長崎ではなく福岡に原爆が落とされていたら、福岡県出身の古賀さんのおじいさんやおばあさんにも影響があったかもしれないですね。こうした古賀さんのアメリカでの経験は、今の活動にどう繋がっているのでしょうか?
古賀:アメリカの原体験があるおかげで、一般的な日本人と比べ、核の問題を考える際日本が被害者でアメリカが加害者という単純な二項対立的な捉え方ではなく、広い視野で捉えられるようになったと思います。そして、核の問題を少しでも解決の方向に進めるには、自分と異なる意見を持つ人と積極的に対話しなければ、何も進まないと感じました。そのためアメリカの大学院に進学したいと思うようになりました。例えば日本では、原爆の話になると、原爆は悪であるとか、核廃絶とか、その方向にしか話が進まず、そこで話が止まってしまいます。でも現実世界では、アメリカを始めヨーロッパの国々などでも核を保有する国は存在していて、その人たちが動かなければ核廃絶は進みません。だとしたら、日本で同じような思想を持っている人たち同士で〝核は良くないよね〟と言い合うだけでなく、自分から外に出て、アメリカのように比較的、核を肯定している人たちとも対話していく必要があると考えました。だから今後も、アメリカで研究を続けていきたいと思っています。


伊沢:私も糞土師になって講演会を開いても、ウンコに関心のある人しか来なかったし、そういう中で十年近く活動をしてきたんです。糞土思想がある程度出来上がってもそのままではダメだから、今度は関心のない人や反対する人にも広めなくては、と思うようになりました。それが、この対談ふんだんを始めたきっかけなんです。そう考えると、古賀さんとも共通項がたくさんありますね。
古賀:関心のない人や、反対する人など、異なる意見を持つ人と対話する際に気をつけていることはありますか?
伊沢:ウンコがどうのこうのというだけではなくて、より根源的な話をするようにしています。例えば、人間が食べているものは全て生き物です。だから食べて命を奪って生きていることを話し、そこから命を返すための野糞が大切だというように話を進めます。
私が野糞を始めたきっかけは、し尿処理場反対運動でした。し尿処理場は臭くて汚い。だから近所にできたら嫌だ、という住民運動です。確かに処理場は臭くて汚いけれど、そこで処理してもらうのは自分のウンコだろう。なんて勝手なんだ、と思ったときに、自分自身もそれまでトイレにウンコをしていたんです。そのウンコはし尿処理場に運ばれて、周りの人に迷惑をかけながら処理されている。トイレにウンコをすることは人に迷惑をかけることだったんです。だから自分のウンコに責任を持たなければと考えたときに、菌類の分解の働きを知って、野糞という答に行き着きました。人に迷惑をかけず、しかも自然環境にはプラスになる一石二鳥の方法として。


古賀:小学校の修学旅行で長崎に行ったのですが、当時、原爆についての展示写真を見て怖かったし、できれば見たくないと感じました。興味もそこまでありませんでした。しかし、同じ原爆投下という歴史なのに、落としたアメリカと落とされた日本とでは何故こうも違う歴史が教えられているのか、興味を持つようになりました。それから核のことを考えるようになったんです。
異なる意見を持つ人と対話する際、私が気をつけていることは、相手の立場や意見に興味を持ち、まずは聞く、ということです。「原爆は悪いもの」という一方的な正義を最初から話すのではなく、相手がどう考えているのかを聞いたうえで、納得してから自分の意見を伝えるようにしています。自分が思っていること、信じていることは必ずしも正解ではないし、他の人の意見を聞いて、やはり自分が考えていたことが正しいと思うことも、逆に相手の言っていることが正しいと思うこともあるはずです。または自分と相手の意見の両方を合わせたものがいいな、と思うことも。だから、自分と意見の異なる人との対話を大事にしています。
伊沢:なるほど。ところが私はまず、自分の意見を先に言っちゃうんですよね。互いに言いたいことを言い合って、それから考える、ということをしてきました。私、とにかくせっかちだから(笑)。でも、最終的には両方の意見を聞いてますけどね。
古賀:喧嘩にはならないのですよね?
伊沢:そこまではやらないです。自分でも知らないことがたくさんあることは認識していますから。ただ、ウンコのことや野糞のことを分かってくれよ、と言う気持ちが強いから、まずしゃべっちゃう。それから相手の反応を見ます。古賀さんは10代から、まず人の話を聞くということができていたなんて、素晴らしいですね。
古賀:大学生の時にドキュメンタリー作品を作り始めて人の声に耳を傾けることの重要性を学ばせていただきました。大学在学中はジャーナリストを目指していました。今回、伊沢さんが新聞記事を読んで私に連絡をくださったように、自分がメディアに出ることで、小さかったことがいろんな人に伝わって、いい影響をもたらしていく。それが社会を大きく動かしているのでは、と思ったからです。それでドキュメンタリー作品を作っていたのですが、今の日本のジャーナリズムにはエンタメに近い要素があるのではないかとだんだん考えるようになったんです。特に自分がメディアにたくさん取材されるようになってから感じたことなんですが、取材する記者の頭の中にはすでに構想が固まっていて、そこに記者が書きたいことだけを綺麗に切り取るので自分が材料としてポンと当てはめられた感覚になったんですよね。それが報道されて大きなものになっていくときに、その報道は誰のためなのかと感じるようになったんです。今の日本のジャーナリズムは必ずしも社会のためではないなと感じました。
伊沢:自分の実態じゃないものに作り替えられていると感じたんですね。
古賀:もちろん報道の質がよければ、それが社会全体に広まりいい方向に向かうと思うのですが、今の日本のメディアは報道する事に必死になりすぎていて、目的を失っているような気がしました。
また、私自身もドキュメンタリー作品を制作していましたが、もしかしたら同じことをしていたかもしれないと考えるようにもなったんです。実際、取材対象者の言葉で、自分が見せたいところだけを綺麗に切り取る、ということをした苦い過去もありました。今振り返ると、社会のためというよりも自分のための活動だったな、と。その頃に大学の卒業論文を通して研究の面白さにも気づき、研究こそ、純粋に真理の探究であり、自分の性に合うと実感しました。だから今は研究員を目指しているんです。研究者になっても勿論発信していくことをしたいですし、研究者と発信者のバランスはこれから取っていきたいと思います。
伊沢:写真家時代の私はキノコやコケなどを撮っていたのですが、自分がアーティストだとは思わなかったんです。当初は自分の内から沸き上がってきたものを写真にするのがアートだと思っていたのが、途中から被写体そのものの素晴らしさに打たれ、むしろ自分を消して、それ自体を正確にフィルム上に再現する、むしろ証拠写真を目指したんです。だから私は一時期、写真家ではなく〝写真職人〟と名乗っていました。そう考えると、古賀さんの思いと似てますね。あくまでも実体をとことん追求したかったんです。


古賀:研究員になることで目指しているのは、核の安全性を解明し、核の被害者を減らすということです。具体的には放射能のリスクがどのように科学や社会で受け止められてきたかを解明することができたらと思っています。
伊沢:放射能の被害を抑えたい、なくしたいというのが一番の目的なんですね。そこには、原爆がもし、長崎ではなくて福岡に落とされていたら、という思いもあるのでしょうか。
古賀:はい、ありますね。もし自分の祖父母が犠牲になっていたら、ということが、自分事として問題を捉えるきっかけになっています。
伊沢:他人事どころか、古賀さん自身が生まれなかったかもしれないですよね。やはり自分事となると一生懸命取り組めます。私はなんで、それがウンコになったんだろう?(笑)豊かな自然のなかで幸せに暮らしたいという思いかな。だからやっぱり自分事なんですね。
古賀:それこそ、福島やチェルノブイリでは放射能被害で、何十年も住めないような土地になっていますよね。環境問題でもあると思います。
伊沢:非常に大切なものとして、「自然の摂理」という言葉がありますね。それは、自然界では全てのものが循環する、ということだと思います。その循環の中に自分を組み込めば、ウンコでも死体でも土に還って新たな命に生まれ変われる。しかしウンコや死体をし尿処理場や火葬場で燃やしたりしては、土に還れないし、次の命にも繋がらない。だから私は、野糞や土葬こそ、環境再生の鍵だと考えているんです。
古賀:すごく大事なことなのに、学校では教わらないですね。
伊沢:そう、教えないんです。今のこの人間社会では、ウンコや死体は完全に汚染物質として扱われているんです。でも私からすれば、ウンコや死体くらいすごい命の素はないだろうと思うわけです。そしてこの考え方を広めないことには、後の世代に対して責任が持てないんじゃないか。
自分の前には先祖から続いてきた命があって、今ここに自分がいる。ならば自分も、後の人たちに対して命を渡していきたい。それが野糞と土葬でできるんだよ、と伝えていきたいんです。
じつは少し前に旭山動物園統括園長の板東さんと対談をしたんですが、そこで板東さんは、野生動物は子どもに命をつなぐために、自分の命を投げ出してでも子どもを守っていることを話してくれました。人間は野生動物を馬鹿にしているけど、人間以上に自然の摂理の中できちんと生きているんです。むしろ見習うべきですよ。
ところで、私はもう70を超えました。私の世代から見ると、古賀さんのような若い世代の感覚は、まったく違いますよね。

古賀:そうですね。私たちは携帯が当たり前にある世代なので、いつでも情報を得たり発信できる環境があります。ただ一方で、オンラインのコミュニケーションは一方通行になりがちで、難しさもあります。私もその点については試行錯誤しています。
伊沢:そうそう、軽いんですよね。方法としては便利だけど、どこまでしっかり伝えられるか。やはり対面のほうが圧倒的に伝わりやすいですね。
古賀:そうなんです。強い言葉や過激な画像、映像を伝えるのには向いているけれど、言葉では表せないニュアンスなどは、ネットでは伝えられないところがあると感じています。特にウンコの話や私の核の話のように、繊細で、これだと断言できないような話は、特にネットでの発信は難しさを感じています。
伊沢:だから今回、まずは古賀さんとお会いしてすぐプープランドに来ていただいたんです。言葉ではなく、肌感覚でその実体を知ってほしかったんです。
古賀:それは本当に重要ですね。
伊沢:私は、今日のように実際に現地に誰かを連れて行く、来てもらうという方法を取っていますが、古賀さんはどのような手段で伝えていこうと考えていますか?
古賀:私自身は、コミュニティを作ることが重要なのかなと考えています。大多数に対しての発信だけでなく、自分の考えに共感してくれる人たちとコミュニティを作り、そこから発信していくことが大切なのではと考えています。そして一方的発信ではなく、お互いに議論する、ということです。
伊沢:そういう場をどんどん作ることが大切ですね。例えば、今はシェアハウスが広がっていますよね。それも一つのコミュニティですが、そういう経験はありますか?
古賀:はい、あります。シェアハウスやゲストハウスを利用したことで、普段は絶対交わらないような人との出会いがありました。そういう機会や場を活用して発信していくことも大事ですね。プープランドという場所もすごくいいですね。ブランコやシーソーやベンチがあったりとか。プープランドの目的自体は難しい話ですが、その入り口が遊び場のような形なので入りやすいと感じました。
伊沢:そうですね。まずはその場の気持ちよさを体験してもらい、そこから「この気持ちよさはどうやって作られているのか?」と考えてもらえればいいんです。今の若い世代がこれからの世界を作っていくと考えているからこそ、私にとっては「うんこと死にしっかり向き合う糞土思想」をどう次の世代に伝えるかが大事です。
私が生まれた戦後の時代は経済的には貧しかったけれど、自然は豊かでした。便利なスマホもテレビゲームもないので、遊ぶ場は自然の中で、それが幸いだったと思います。今は豊かな時代で面白いものが身近にたくさんあり、自然に出なくても楽しく過ごせます。自然に触れる機会がなくなった、というか自ら放棄していて、そのことにさえ気づかない人も多いんでしょうね。
古賀:確かに今は便利なものが多く、自然に触れる機会が減っていますね。
伊沢:そうなんです。だから私は、言葉で伝えるよりも、体験を通じてそのことを伝えたい思っています。屋内での講演会だけではなく、実際に野外でフィールドワークをやると、反応が全然違うんです。だから私は糞土塾やプープランドを始めたんです。言葉よりも体験を通じて伝える。肌感覚で伝える。それが一番ですね。だからこれからは、全国各地にプープランドを造る運動を進めます。
古賀:体験できる場所を増やすんですね。
伊沢:そうです。あちこちに造って、そこに行けば誰でも体験できるようにしたいんです。古賀さんは今、ジャーナリストから研究者に転向して、これからその探究が始まりますね。もう目指すところはあるんですか?
古賀:私自身はまだ、核に対する自分の考えが固まっていない段階です。答えが見えていないから、だからこそ研究を選びました。核兵器をなくすべきか、そうじゃないのかという答えが、自分なりにまだ出ていません。広島や長崎にいれば、核兵器はないほうがいいと簡単に言えますが、実際に核が抑止力として働いて、冷戦時代、そして今も使われなかったという論理もあるわけです。でも今は、核の抑止がどんどん弱くなっている中で、アメリカ国民も核を使うべきではないという意見が強まっていて、大量虐殺を起こすような核兵器は使うべきではないという意見が大多数なんです。でもひとつ言えるのは、放射能被害は人の一生を狂わせるものなので、核兵器はこの世界から無くすべきじゃないかという思いをもって、私は研究に臨もうとしています。ですので私は、これからです。そういう意味で、今プープランドを広げていこうという目的を明確に持っている伊沢さんは、私にとって先輩です。

伊沢:私はここにくるまでに、本当に長い年月がかかりました。そして今は言葉の軽さを実感すると共に、新たな気付きもありました。これまでは人々の生き方の指針として宗教の教えがあり、それを信じ、実践することで善い社会になると思っていました。しかし時代が進むにつれて人間社会の形態が大きく変わり、その影響で自然環境が極端に悪化しました。以前からの教えよりも、現状に対応する科学的な探究こそ重要です。過剰な人間活動による環境破壊を、これから環境再生に転換する指針が糞土思想にあると考えています。
私はあと何年この活動を続けられるか分かりません。だからこそこの糞土思想を、次の世代に繋いでいかなくてはと考えています。自分の終わりを見据えて、いかに自分の想いを伝え引き継いでもらうかですね。そしてそういう受け渡せる状況が見えてきたことに喜びも感じています。
古賀:今日、糞土庵やプープランドを訪れて感じたのは、体験する場所を提供して、こちらから一方的に教えるというよりは、体を動かして皆に感じてもらうのがすごく大事だなということです。プープランドで、みんなで体験する。そういう場を、自分の研究分野でもどうやって作っていけるのかを考えるようになりました。
伊沢:嬉しい〜、伝わったよ〜(涙)。どうもありがとう。新しい時代のために、よろしくお願いします!

<完>
撮影・編集:小松由佳