高田宏臣(NPO法人地球守 代表理事)×伊沢正名(糞土師)

藪で覆われ、乾いた地面が続く、荒れ果てた森。そんな森を、独自のアプローチで再生させてきた人物こそ、造園家の高田宏臣さんです。「土も、呼吸ができなければ苦しい。人間と一緒です。」そう話し、水と空気の循環、そして生命の循環という観点から土を捉えるその手法は、糞土思想とも大きなつながりがありました。
人間は、「良い森」を感じられる
伊沢 今日は高田さん率いる「NPO法人地球守」が運営する、千葉県のダーチャフィールドに伺っています。ここは荒れた森を再生して作った場所なんですよね。
高田 はい、そうです。ここで自然体験のイベントを開くこともあれば、森の再生作業を子どもたちに手伝ってもらうこともあります。いまお話をしているこの小屋は、解体民家の古材を再利用して建てました。

対談を行なったダーチャフィールド内の小屋。環境をなるべく壊さぬよう傾斜地をそのまま活用するため、石の上に柱を建てる伝統的な工法で建てているそう。
伊沢 そんな活動をされながら、高田さんは2020年に、『土中環境』というご著書を上梓されました。「土中環境」とは聞きなれない言葉ですが、改めてどういう意味なのですか?
高田 似ている言葉に「土壌環境」がありますが、全く違う言葉です。土壌環境は、土の成分や性質などの表層部分を指しますが、土中環境は、循環という観点から、土をより総体的に見る言葉。土中で水と空気が循環して、土がきちんと呼吸できているか、生き物の循環が生まれる環境になっているか。そういった視点を大事にするアプローチなのです。
伊沢 土を「生き物」として捉えているのですね、面白い!
高田 荒れ果てて草木が育たない場所でも、土が呼吸できるように水と空気の通り道を作れば、大幅に土中環境を改善できます。肥料や薬を撒くのではなく、このアプローチで土木設計や造園を担うのが、私の仕事です。
著書を出すときは、「こんなマニアックな言葉がタイトルで良いのか」という葛藤もありました。ですが、今まで見過ごされてきたこの土中環境こそ、注目されていかねばならない。その思いと決意を込めて、タイトルを付けました。
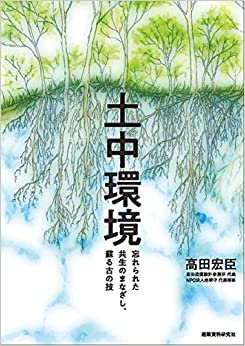
2020年に高田さんが上梓した著書。従来の土木のあり方を根本から問い直す、目からウロコが連続の1冊。
伊沢 たしかに土中環境のアプローチは、あまり知られていませんね。高田さんはなぜ、土中環境に目を向け始めたのでしょうか?
高田 原体験としてあったのは、高校生の頃に一人で森を散策していたときの感覚です。一人で森にいると、感覚的に「この森は、良い森だ」とわかるんですね。きちんと呼吸できている健康な森と、荒れ果てた森では、見た目も香りも、聞こえてくる音も、全て違う。
良い森では全部が心地よくて、包み込まれるような安心感があるんです。この感覚が、人間には何万年も前からDNAに刻み込まれているんだと思います。
伊沢 わかります。私も若い頃は「仙人になりたい」と思って、高校を中退して山にこもっていました。山の中では、夜になると特に、いろんな音が聞こえてきます。最初は怖かったのですが、だんだんと「これは鳥が歩く音だ」「風の音だ」とわかってくる。自然を知るには、やはり一人で自然の中に入り込むのが一番ですよね。
高田 そうですよね。ですが、森林分野の大学を卒業して造園家として働き始めると、やはり農薬や除草剤を使った施工をするようになります。それが一般的に行なわれる“正しい”方法ですから。
ですが年を経るにつれ、そのやり方に疑問を感じるようになりました。考えを変えるきっかけの一つになった出来事があります。裏山を背負った住宅開発の際、国の宅地造成許可基準をクリアするために、山の斜面を削ってコンクリートで固めたことがありました。

無事に建築・造園工事を終えましたが、その後、裏山はみるみる荒れてしまったのです。コンクリートで固めた付近だけでなく、山全体の土が乾燥し、雑草ばかりが生えてきて、私が知っている「良い自然」とは、全く異なるものになってしまった。これは工事によって、土の中の水と空気の流れを遮断してしまったことが原因でした。
自分が培ってきた「良い自然」の感覚と、自分が自然に対して行なっていた土木工事が、全く噛み合っていない。そんな違和感に30代はじめで気づき、土全体が呼吸できる環境を整える土中環境の重要性に、目を向けるようになったのです。









